「神さまは愛の行為しかなさらない」
- 2025年12月19日
- 読了時間: 9分
原山建郎氏の新作『遠藤周作の「病い」と「神さま」』をお届けいたします。今回は、第二章の3「神さまは愛の行為しかなさらない」です。
第二章 僕が神を棄てようとしても、神は僕を棄てないのです。
3.「神さまは愛の行為しかなさらない」
☆憎しみは、相手に執着があるから、相手を憎むのではないか。
もう一つ、遠藤さんの幼少期、最愛の母・郁を裏切り、棄てた父・常久の存在があります。
遠藤さんの著書、『生き上手 死に上手』(文藝春秋、1994年)には、【愛した者と再会できる。そういう世界が死のあとにある。母や友人や兄弟に再会できるための死。そういう死なら我々はもうこわくはない。】と書かれていても、「父に再会できる」とは書かれていません。晩年になってから、順子夫人による和解のすすめで、病床の父を見舞うようになりますが、1989年、父が93歳でこの世を去る日まで、終生、この父を憎み、許さなかったといいます。
『死について考える』(遠藤周作著、光文社文庫、1996年)に、次の一文があります。
日本には現世の利益を願う新興宗教がたくさんあります。(中略)キリスト教信者の中にも、現世利益だけを求めて信仰している人が実際にいくらでもいます。子供が白血病になり、一所懸命に神様にお祈りしたけれども、子供は死んでしまった。神なぞ何だ、と神を憎む、神も仏もあるものか、というところから宗教は始まるのではないでしょうか。
神を憎むことも、神の存在をはじめから無視している無宗教や無関心ではなく、憎むということで神を強く意識していることです。神があろうがなかろうがどうでもいいという無関心より、神を憎むことのほうがはるかに宗教的でしょう。
(『死について考える』167~168ページ)
☆「あたし、神さまなど、あると、思わない」
たとえば、『わたしが・棄てた・女』(講談社、1969年)では、容態が悪化したハンセン病の子ども(壮ちゃん)を看病しながら、主人公の森田ミツは「壮ちゃんを助けてくれるなら、そのかわり、あたしが癩病(※ハンセン病)になってもいい」とつめたい木造病棟の床にひざまずいて祈りますが、その甲斐もなく、その5日後、壮ちゃんは息を引きとります。
ミツは「あたし、神さまなど、あると、思わない。そんなもん、あるもんですか」とひどく嘆きます。
そして、「なぜなの? 壮ちゃんが死んだから? あなたの願いを、神が、きいてくれなかったから?」という修道女の問いに、ミツは「あたしさ、神さまがなぜ壮ちゃんみたいな小さな子供まで苦しませるのか、わかんないもん。子供たちをいじめるのは、いけないことだもん。子供たちをいじめるものを、信じたくないわよ」と答えています。
また、大津に言わせた「ぼくが神を棄てようとしても、神はぼくを棄てないのです」のなかの「神」を「父」と置きかえると、「遠藤周作」ものがたりにおける最大の敵役、父・常久の存在が、イニシエーション(通過儀礼)、困難な旅におけるトリックスター、遠藤さんの人生にターニングポイントをもたらす、大きな役割を果たしたと考えることができます。
☆ 「神さまは、愛の行為しかなさらない」
2016年12月、私はNHKラジオ第二放送「宗教の時間」に出演し、「神は愛の行為しかなさらない~遠藤周作・心あたたかな医療」について話しました。
はじめに、遠藤さんが提唱した「心あたたかな医療」キャンペーンの広がり、首都圏の病院・介護施設で続く「遠藤ボランティア・グループ」の活動を紹介し、後半では『僕のコーヒーブレイク』(遠藤周作編著、主婦の友社、1981年)にも載った奇跡のエピソード、山崎泰広さんの物語を紹介しました。
1979年(昭和54年)2月、山崎泰広さんは留学先のハイスクールで、寄宿舎の窓からの転落事故で脊椎損傷を負いました。
転落事故に見舞われた直後、急遽、渡米した彼の母親で童話作家でもある山崎陽子さんは、まだ深刻な病状を知らない息子に、彼の下半身が絶望的であると言い出しかねて、悶々とした思いでいたときに、友人である遠藤周作さんから、次のような手紙をもらいました。
そこには、「神さまは愛の行為しかなさらない。自分もかつて何度も病の床について、なぜ自分だけがこんなに苦しまなくてはならないのかと、神さまを恨んだことがありました。しかし、いま振り返ってみると、やはり神さまは愛の行為しかなさらなかったと思います。今回の事故も、坊ちゃんにとってよかったということにいつかなるでしょう」と書かれていました。
しかし、陽子さんは病院にある小さなチャペルのマリア像の前にぬかずき、「こんなひどいことが、愛の行為であるはずはない。イエスさまが十字架にかかった、あんな悲しい思いをされたあなたは、母親の悲しみをよくご存知のはずなのに、なぜこんなひどいことを。マリアさま、いますぐ息子の足に奇跡を起こして」とひたすら祈ったのです。
下半身麻痺となった泰広さんは、病院を訪れた神父さんから「一緒にお祈りしよう」と声をかけられます。「私はお祈りの文句を知らない」と答えると、「神さまに感謝することができれば、それがどんな言い方だって、何語であってもいいんだよ」と励まされ、さらに神父さんはこうも言われました。「たとえば、君には何の障害もない手がある。脳だって完全だね。それから今日はどんな日だった? いい日だったかい。どんな人に会ったかね。楽しかったかい。ほーら、いろんなことに感謝できるじゃないか」と。
陽子さんは遠藤さんとの対談で、そのときのことを次のように述べています
山崎 そんなふうに本人が何も(※下半身不随に重傷を負ったことを)知らないときから、毎日いらしてお祈りしてくださった神父さまがいらしたんですね。神父さまというよりは、船乗りみたいな感じのかたで、(笑)カラーだけで神父さまってわかるような武骨な感じのかたが、毎日来てくださった。「ハロー、ハンサム」って入っていらして、手を握って「きょうはどこが痛い?」とお聞きになるんですね。どことどこが痛いっていうと、「そうか」と言って「この痛みをとり去ってください」とお祈りなさるの。ときどき床ずれができないように、ベッドがまっさかさまになって、顔が床のほうに向いているわけですが、そんなとき、神父さまは、床にあおむけに寝てお祈りしてくださるのです。それを見ていると、いつも涙が止まらなくなりました。ひと言もキリスト教の話をなさらなかったし、キリスト教徒になれとも、何一つそのことに関してはおっしゃらずに、ただ手を握って 「どこが痛いんだ」って。息子が、パペロニのピッツアが食べたいと言うと、神父さまがそれをご自分で焼いて、上着の中に隠して(笑)病院が閉まった時刻に忍び込んでいらして「食べないか」とくださる。退院まで一日も欠かさずにいらしてくださいました。そして手は間もなく動くようになるんですけれど、下半身が絶望的で、そのことを本人にはっきり告げなさい、とお医者さまがおっしゃるんですね。
遠藤 つらかったろうなあ。
山崎 患者には知る権利がある、とおっしゃるの。日本人は言わないのが主義かもしれないけれど、知る権利があるから、すぐ言いなさいと。母親が言わないのは過保護なのかって。だから私は「自分自身がまだ信じられないから言えない」って言ったんです。
(『僕のコーヒーブレイク』54~55ページ)
また、やはり陽子さんの友人である作家・三浦朱門さんに、「できることなら、母親である私が息子の運命を代わってやりたい。私はすべてを犠牲にして、彼の足になってやりたい」という意味の手紙を書きましたが、三浦さんからの返信はとてもきびしいものでした。
「もし、泰広君が母親を犠牲にして幸せになることを喜ぶような息子だったら、彼には母親に犠牲になってもらう価値はない。また、母親であるあなたなら運命を代わってやれるが、息子にはとてもその試練を乗り越える力がないと思うのなら、あなたは息子さんを見くびっていることになる」
☆ 「あなたの息子に、私の足をあげたい」
ある日、泰広さんは自分の下半身が絶望的であるということを知ります。そのとき、彼は頭を冷やしていたガーゼを眼の上にスッとずらしました。陽子さんはハッとしました。
しかし、その次の瞬間、ガーゼをパッとはねのけた彼は、「(立てないからといって)ぼくが不幸になるはずはない」と言って、にっこり微笑んだのです。
翌朝、病院を訪れた陽子さんのところに、一人のおじいさんがやってきて、「私があなたの息子に自分の足をあげたい、と言ったら、彼は〈おじいさんは70年近く足を使って、とても苦労して生きてきたんだから、これからはその足を使って楽しい人生を送ってください。ぼくのことを若いからかわいそうだと思うかもしれないけれど、十代だからこそ足のない人生だっていくらでも描けます〉と言われた」と言ったんだと、おいおい泣きながら、あなたの息子がいまに実業家になったら、私を守衛に雇ってくれと、自分の住所と名前をおいていきました。
その後、泰広さんが退院するまでの間、事故で手足を切断したり、下半身不随になった患者がいると、彼はその病室を訪れて励ますようになり、やがて「ミスター・インディペンデント」と呼ばれるようになったのでした。
その後、泰広さんはボストンカレッジ経営学部でマーケティングとコンピュータ科学を学び、帰国後、身障者関連機器の輸入販売とコンピュータコンサルティングを行う会社を設立しました。1992年のバルセロナ・パラリンピックでは三種目に出場し、100メートル平泳ぎで6位入賞を果たしました。1999年には日本身体障害者社会人協会を設立しています。
☆ 「奇跡」とは、立てない足が「立つ」ことではない。
わが子の身代わりになりたいという陽子さんに、厳しい手紙を書いた三浦さんは、『僕のコーヒーブレイク』の対談で、次のように述べています。
遠藤 たとえば、ぼくと三浦の共通の友人の坊ちゃんが、半身不随になられたとき、ぼくはお母さんを慰めるのに、神さまというのは、けっしてどんなときも悪いことはなさらないから、事故ということも、坊ちゃんにとってよかったということにいつかなるでしょうと書いた。そして現実になりつつあるんだけれど、しかしそこまでになるのがたいへんだよなあ。
三浦 うーん。
遠藤 神の摂理だけじゃなくて、こちらの努力で、そう転嫁しなくちゃあいけないだろう。その坊ちゃんは、非常に努力されたけど。そういう事故がなくて、そのままずっといってらしたら、それは非常にけっこうだったろうけど、事故によって、そのままではけっしてつかめない、人生の奥行と深さが違ってきたと思う。
三浦 ぼくは残忍酷薄な人間だから、奇跡というのは、立てない足が立つことじゃない、と言った。
遠藤 ぼくもそう思う。
三浦 奇跡というのは、立てないでも、立つことよりもそのほうがよかったと思うとき、そのとき奇跡が訪れたんだ。
遠藤 うん。
三浦 ぼくは、世の中にありうべからざること、理論的に説明のつかないことが起こったってかまわないけど、それも奇跡だと思うけど、それだけが奇跡じゃなくて、どんな状態でも、考えもつかないような結果を生むこと、それが奇跡だと思う。
(『僕のコーヒーブレイク』75ページ)
〈からだ〉は車イスに座っていても、〈こころ〉は立派に立っている。かつても、そしていまでも〈ミスター・インディペンデント〉、山崎泰広さんの「奇跡」の物語はつづいています。
♠ マハトマ・ガンジーのことば 3
幸福とは、考えること、言うこと、することが調和している状態である。(Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. )


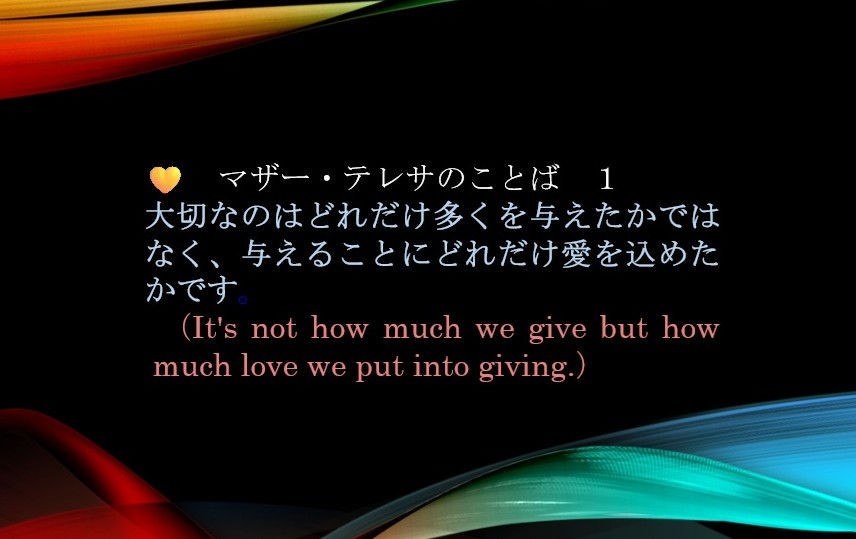
コメント